豊かな自然と地域づくりの里 |
 〒646-0001 和歌山県田辺市上秋津地区 上秋津地区はほぼ半分にわたって自然がのこされ、開墾地が約30%。緑が全体の8割近くを占めます。春には桜、夏には新緑、秋は紅葉、冬は梅。四季四季に草木が景色に彩りをそえ、日々の暮らしを和ませてくれます。また名勝旧跡が点在し、神の悪戯ともおぼしき巨岩、怪石の群は吉野熊野国立公園に指定されています「奇絶峡」あるいは「高尾山」「竜神山」「三星山」をはじめ数々の山々と一年を通し、ウォーキングやハイキング、史跡探訪にと市民にしたしまれています。 たくさんの自然が残された上秋津では、一年を通していろいろなイベントが催されています。田辺市民なら子供の頃一度は登る高尾山では、高尾山登山などのイベントも行われています。  農業の盛んな上秋津では秋の収穫を祝う祭りもにぎやかで、地区外からもたくさんの人々が訪れます。このほか、みかんの収穫体験など地域の特色を活かした催しに取り組み、県内外との交流も深めています。また、明治時代の大水害で高尾山には崖崩れが起こり、人文字型のハゲになっていました。この崖崩れは長い間、田辺市民に災害への警告とともに高尾山の象徴として親しまれていましたが、当初は「上秋津を考える会」が、その後人文字をともす会が中心となり、今はないこのハゲを復活させようと、お盆とお正月の各1週間、人文字を灯らさせるのも、いつのまにか紀南の風物詩となりました。また、公益社団法人上秋津愛郷会の所有の山林となっている高尾山の中腹から山頂にかけて採れる松茸は有名で、秋が近づくと収穫地が区画され、一般入札されます。その年によってどの区画がよく
採れるかは不明で、毎年話題となり市民を楽しませています。 農業の盛んな上秋津では秋の収穫を祝う祭りもにぎやかで、地区外からもたくさんの人々が訪れます。このほか、みかんの収穫体験など地域の特色を活かした催しに取り組み、県内外との交流も深めています。また、明治時代の大水害で高尾山には崖崩れが起こり、人文字型のハゲになっていました。この崖崩れは長い間、田辺市民に災害への警告とともに高尾山の象徴として親しまれていましたが、当初は「上秋津を考える会」が、その後人文字をともす会が中心となり、今はないこのハゲを復活させようと、お盆とお正月の各1週間、人文字を灯らさせるのも、いつのまにか紀南の風物詩となりました。また、公益社団法人上秋津愛郷会の所有の山林となっている高尾山の中腹から山頂にかけて採れる松茸は有名で、秋が近づくと収穫地が区画され、一般入札されます。その年によってどの区画がよく
採れるかは不明で、毎年話題となり市民を楽しませています。こういった地域の豊かな自然や農業を活かした地域づくりが住民の手で進められています。その一環として平成11年には秋津野直売所『きてら』、平成20年には都市と農村の交流施設秋津野ガルテンを誕生させました。 |
かつては秋津野の里と呼ばれていました |
 かつて秋津野と呼ばれていた上秋津は、田辺市のシンボル・高尾山の北側、名勝・奇絶峡(きぜっきょう)より南に流れる会津川流域から山麓一帯に拓かれた古い歴史をもつ里です。 かつて秋津野と呼ばれていた上秋津は、田辺市のシンボル・高尾山の北側、名勝・奇絶峡(きぜっきょう)より南に流れる会津川流域から山麓一帯に拓かれた古い歴史をもつ里です。また高尾山の西には会津川をへだて竜神山や三星山がひときわ緑濃い自然のたたずまいを見せています。 上秋津は数々のいわれと伝説に彩られ、いまなお人と自然がともに暮らす里です。 平安朝時代、このあたり一帯は藤原氏の荘園として治められていましたが、このころ、高尾山中腹には千光寺が、建立されていました。千光寺はのちに焼け落ちたといわれていますが、本堂跡には歴史的にも貴重な3つの経塚が発掘されています。銅鏡や経筒などの出土品は東京国立博物館や田辺市の歴史民族資料館に保管、展示されています。  戦前までは上秋津周辺を「秋津野」と呼んでいました。しかし現在は「秋津野」という地名はありませんが、秋津野橋という名の橋が存在しています。時代と共に人々には忘れ去られていました。 上秋津中学校の新築を機に、当時のPTAが広報誌名に秋津野の名を復活させ。平成6年には、地域にある24団体で組織した地域づくり協議団体『秋津野塾』が誕生してからは、人々は再び秋津野の名称を再び使いはじめました。 平成20年に地域住民が上秋津小学校跡地で起ち上げた、都市と農村の交流施設の名を『秋津野ガルテン』として、その名を残しました。 |
万葉の歌人、柿本人麻呂と秋津野 |
| 万葉の歌人、柿本人麿呂が、「常知らぬ人国山の秋津野の杜若を夢に見しかも」と詠った風情ゆたかな上秋津はいまもその面影をいたるところにとどめています。
現在「秋津野」という地名はありませんが、秋津野橋という名の橋が存在しています。 広辞苑には、「あきず(あきつ)とはトンボの古名、秋津島とは日本国の異称。 1.古代奈良の吉野離宮周辺の野。 2.和歌山県田辺市の北の野。 と記されています 万葉の歌人、柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)が、秋津野を詠んだふたつの歌を紹介します 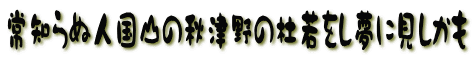 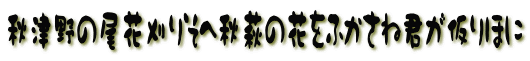 |

秋津野の里
 TOP
TOP カゴの中
カゴの中 発送・送料
発送・送料 支払方法
支払方法 特定商取引法
特定商取引法 連絡先
連絡先 会員メニュー
会員メニュー
 新規会員登録
新規会員登録 パスワードが不明な方
パスワードが不明な方 CLICK
CLICK
 キーワード検索
キーワード検索
 商品番号で表示
商品番号で表示
 カテゴリ一覧
カテゴリ一覧

 商品一覧
商品一覧